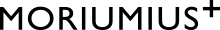北上川の恩恵を受けた県内有数の穀倉地帯・宮城県河南地区(現在は合併して石巻市)に、モリウミアスをオープン時より支えるササニシキ農家「田伝むし」はあります。モリウミアスの食事で提供されるお米は全て、田伝むしの無農薬ササニシキ胚芽米です。田伝むしの代表を務める木村純さんは、1987年に両親が始めた無農薬栽培を引き継ぐため、2005年に脱サラして就農。以降、農協を通さず独自の販売ルートを開拓し、こどもたちが安心して食べられるように、無農薬のササニシキを手間ひまかけてつくり続けています。そんな木村さんにお話を伺うため、田植え直前の田伝むしを訪ねました。
ファンのために希少価値の高いササニシキをつくり、届ける
――田伝むしではササニシキを無農薬で栽培しているそうですが、ササニシキはどんな特徴があるお米ですか?
コシヒカリのように、甘みが強くモチモチした食感の品種に対し、ササニシキは甘みが少なくあっさりとしていて、冷めても美味しいのが特徴です。そのササニシキの特徴を活かしたのが寿司で、シャリが出しゃばることなくネタを引き立ててくれるので、寿司飯として人気です。食卓でも、特に煮魚や焼き魚など、和食との相性は抜群です。
――まさに新鮮な魚介が多い石巻一帯に適したお米なのですね。この辺りでは米農家といえばササニシキなのでしょうか。
石巻市でも特にこの辺一帯は、ほとんどの農家がササニシキを生産していたササニシキの里でした。今も生産量は日本一です。平成5年の大冷害でその影響をもっとも受けたのがササニシキでした。それ以前はコシヒカリに次ぐ全国2番目の作付けだったのですが、平成5年以降生産者が激減し、現在は0.2%ほどになってしまいました。ササニシキは店頭からも姿を消し、希少価値の高い品種になってしまったのです。

そのため、うちでは冷害に強いササニシキを育てるよう心がけています。稲は苗でその年の作が決まるといっても過言ではなく、田植え前の稲は木製トンボで上から撫でつけ、刺激を与えることで茎を太くし、根張りをよくします。ハウスも本来なら朝夕は窓を閉めて加温するのですが、今のうちから冷たい環境に慣れさせるため、あまり加温もしません。


――それほどササニシキ農家が減ってしまったにもかかわらず、木村さんがササニシキをつくり続けるのはなぜですか?
一番はこどもの頃から食べてきたササニシキが好きだからですね。また、うちは父親の代から無農薬でササニシキを栽培する米農家でした。こどもたちに安心して食べさせられる無農薬栽培の重要性はもちろん、モチモチした食感の米が主流のなか、「やっぱり木村さんのお米がいちばん美味しい」と言ってくださるお客様もいて、それならササニシキをつくり続けようと思ったのです。農家って単純で、その一言だけで頑張れたりするんですよね。
でも、僕らの世代は農家を継ぐ人なんてほとんどいませんでしたから、最初は継ぐのが嫌で、水産加工食品会社の営業など、仙台で10年ほどサラリーマンをしていました。実家に帰るたびに「いつ継ぐんだ」という両親からの圧力を感じて、その呪縛から逃れるように家にもあまり寄り付かなかったんです(笑)。でも、結婚してこどもができたときに、「自然の中で子育てしたい」と言った妻の言葉で踏ん切りがつきました。

僕は単純でそうなると切り替えも早く、全量農協を通さない方法に切り替えようとか、個人向けにネット販売もしていこうとか、せっかくやるなら新しいことをどんどん取り入れようと思ったのです。それからは東京の展示会へ何度も足を運んで、うちのよさを理解してくれる取引先をコツコツ増やしてきました。そんなときに震災が起きて一時はお客様も半減したのですが、モリウミアスとの出合いなどもあり、最近ようやく回復してきたところです。
田んぼの楽しさ、温かさを感じてほしい
――木村さんの田んぼには、毎年モリウミアスのこどもたちが田植えと収穫に来るそうですね。
今年でもう3年目ですね。虫を追いかけたり泥にまみれたり、こどもたちがあそこまで無邪気にはしゃぐ姿は、僕たちにとっても喜びです。田伝むしの田んぼにはザリガニやカエル、秋には赤とんぼ、そしてそれらの餌となる生物がいて、豊かな生態系をつくっています。こどもたちにとって格好の遊び場ですよね。大人だって楽しいはずです。最近では赤とんぼを準絶滅危惧に指定する県もあり、赤とんぼがいなくなってしまったのは農薬の影響ではないか、とも言われています。


我々の親世代にとって農薬は、重労働の草取りから解放される魔法の薬だったわけですが、それに長い間恩恵を預かった結果、生き物がいない田んぼになりつつある。この効率重視の時代に、無農薬は手がかかることは間違いありません。でも、こどもたちが真剣に遊んでいる様子を見ると、やっぱり豊かな自然環境を残していく必要があると強く思うんです。
欧米では耕作面積の20%以上がオーガニックの国もありますが、日本では0.5%と世界の流れから取り残されているのが現状です。オーガニックは生き物の命や環境を維持するだけでなく、こどもたちの教育の場にもなります。「オーガニックは一部の富裕層の人々が選択する手段」というイメージもまだまだありますが、そうではなくいろんな要素を秘めているということを、もっと多くの人に知ってほしいと思います。

微生物がいない田んぼってひんやりするのですが、微生物が豊富な田んぼは足を入れると温かいです。ここに来るこどもたちには、田んぼを肌で感じてほしいですね。パソコンにスマートフォン、私たちの周りは電磁波であふれていますが、日々体に帯電しているものをアースするためにも、年に数回は裸足で土を踏んでその温かさを感じること。それが健康、ひいては幸せにも繋がると思うのです。そしてこうした環境や命の営みがあり、様々な過程を経てお米ができることを、楽しみながら理解してもらえたら嬉しいです。
僕自身、農家は魅力的な仕事だし、稲を育てることほどおもしろい仕事はないと思っています。田んぼで汗をぶったらして働き、体はクタクタになりますが、西に夕日が沈む瞬間に「今日も働いたな!いい1日だった!」という充実感を味わう。これが働くことの原点ではないでしょうか。そう考えると、あのとき農家を継ぐことを渋っていた自分は何だったんだろうって(笑)。
持続可能な仕組みを模索する
――田伝むしでは「おこげ煎餅」や「もみがら玄米スープ」など、ササニシキを原料にした加工品をつくり、様々な形で美味しさを伝えています。
加工品は震災前から、全国の加工会社さんに協力していただいてつくっています。加工品にすることで中米(規格外の米)を有効活用できるのと、新しい収益モデルにもなると考えたのです。僕が将来ササニシキの生産者ネットワークをつくったとして、うちの米が足りなくなったらほかの農家の米で賄う形で回していければ、その農家の収益にもなります。加工品は先を見越したチャレンジでもあり、この先第二の柱にしていければいいですね。

――そのための人材育成にも力が入りそうですね。
うちでは今2人雇用しています。2010年に法人化したのも、雇用して僕らの次に続く人材を育成したいと考えたからです。ただ、日本人の主食を育てるわけですから、「一人の人間の健康をも左右するものをつくっている」、その意味を理解したうえで、食料をつくるに値するマインドが伴った人材でなければいけません。
今考えているのが、人材育成のためのスクールです。僕たちと同じようにオーガニックでお米づくりをしたいという人を受け入れ、一緒に学び、育てていくための環境やしくみづくりです。さらに、オーガニックのお米づくりと持続可能な農業を実現させるための販売の両方を実践で習得し、みそ、ぬか床、干しいも、梅干など、自給できる手づくりの技も会得してもらいます。非農家の方が農家になるのは現状は難しいのですが、農機具の共同利用、販売活動を一緒にやること、私達の農地を貸すことで独立のハードルを下げ、農を取り入れたライフスタイルをしたいというニーズにも応えられるようにできればと考えています。
米は日本人にとって欠かせない食べ物
――色々なチャレンジをされていて、今後の展開が楽しみですね。木村さんがお米づくりを通して伝えたいことは何ですか?
やはり、日本人にとってお米はなくてはならない食べ物だということです。パンや麺など小麦系の食べ物も多い中で、日本人の腸が喜ぶ食べ物といえばご飯や味噌汁、漬物や魚料理といった伝統的な和食です。これらを毎日食べていれば健康を維持できるはずなんですが、ライフスタイルや思考の変化で、悲しいことに米の年間消費量が約8万トンずつ減っているといわれています。米=太るという間違った認識がありますが、味噌汁(酵素が生きた本物の味噌を使ったもの)と一緒に食べればそんなことはありません。稲作が縄文時代から行われていたこと、新嘗祭など米を大切にする文化があったことなどを考えると、日本人にとってお米は特別な食べ物だということがわかります。

こどもたちに伝えたいのは、大きくなる、足が速くなる、ボールを遠くに投げる、全てのパワーの原動力はご飯(米)だということです。朝ご飯をしっかり食べると頭も冴えて、勉強もはかどります。誰もが知っている基本的なことかもしれませんが、米農家として、日本人として、改めてその重要性を伝えていきたいと思っています。
木村純
株式会社田伝むし 代表取締役。2児の父親。代々農家の家に生まれ、高校卒業後はマルハ株式会社(現・マルハニチロ株式会社)などでサラリーマンを経験したのち、2005年に家業のササニシキ農家を継ぐため退職して就農。以降11.5ヘクタールの田んぼで無農薬のササニシキやもち米を栽培し、農協を通さず販売する。2010年に株式会社田伝むしとして法人化。その一連の活動が数々のメディアで取り上げられる。
撮影/永峰拓也 文/開洋美