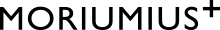アートディレクターを経て写真の道へと進み、第一線で活躍し続ける蓮井幹生さん。東日本大震災をきっかけとするモリウミアスとの出会いから、これまで4度の写真ワークショップをこどもたちに向けて行っていただきました。そして、今年の5月3日〜5日、5回目となるワークショップがモリウミアスで開催されます。蓮井さんが写真を通してこどもたちに伝えたいこと、写真に対する思いなどを、都内にあるご自身のアトリエ兼ご自宅で語っていただきました。
モリウミアスと出会うきっかけとなった被災地支援
震災直後から石巻を中心に支援活動を行う中、ある方の紹介で油井さんに出会い、何度か一緒に炊き出しなどをするうちにモリウミアスの存在を知りました。
その頃は震災から2年経ち、物資の供給も落ち着いてきていたので、メンタルケアのために被災された方々と話をしようと数カ所の仮設住宅に通い、そこで生活する人々の写真を撮らせていただいていました。石巻をはじめ、仙台、登米、二本松、色々な仮設住宅を回り、雄勝にも3回ほど足を運びました。自分のもっている写真の技術で何かできればと考え、被災者の方が離れて暮らすご家族に近況報告ができるよう、写真をポストカードにして切手と一緒に手渡したり、傷んだ写真の修復などに携わっていたのです。

――震災直後から数年かけて被災地に通われた理由は何だったのですか?
もとを辿ると、僕はパレスチナやベトナムの支援活動に携わってきました。パレスチナは日本の市民団体を通じて、現地の聴覚障害児のための聾学校建設への寄付、旅行で訪れたベトナムでは運命的な出会いがあり、ベトナム戦争の後遺症を受けたこどもたちの支援活動を行ってきました。支援については賛否両論ありますが、僕が思うのは、「今の恵まれた状況は必ずしも自分の力ではない」ということです。たまたま平和な日本に生まれ、ご先祖様のお陰で大きな苦労もなく生活できている。そこに溺れず感謝の気持ちを忘れないことは、人生において最も大切な根本だと考えています。
東日本大震災も、自分はたまたま被災しませんでしたが、一つの国や民族としてその状況とどう向き合うかはとても大事なことです。それまでは海外に向いていた意識が、同じ日本の中でこんなに大変な思いをしている人たちがいるなら、自分のできる範囲で力になりたいと思ったのです。
自分自身の「ワクワクする」「気持ちいい」という感覚に自信をもつ
――海外のこどもたちの支援をされていたのですね。その後モリウミアスとの繋がりが生まれ、写真のワークショップも5回目です。こどもの頃に蓮井さんから写真について学べるなんて、本当に素敵な体験だと思います。
今回はモリウミアスを現代美術館にしようかなど、色々考えを巡らせています。今は携帯電話にカメラが付いているように、昔に比べて写真が身近なものになりました。こどもでも上手に写真を撮りますから、僕のワークショップでは技術よりもコンテンポラリーアートとしての写真、というと少し難しいかもしれませんが、写真を通して「アート・美って何?」ということをこどもたちに考えてもらえればと思っています。
――これまでのワークショップでは具体的にどんなことを?
最初の年は、ゴミでも何でもいいから「きれい」だと思うものを拾ってきてこどもたちに白い紙の上に並べてもらい、僕がライティングして撮影してもらいました。単なるゴミでしかないプラスチックの塊や木の枝も、白バックにぽんと置かれて写真になるとかっこいいし、まるでコンテンポラリーアートのようでした。つまり、「それをゴミとしての価値しかないと人間が決めつけているだけ」ということをこどもたちにわかってほしかったのです。ゴミだろうが何だろうが、あなたの感性が一つの絵として美しいと思えばそれが「アート」なんです。
周りの目を気にしたり他人が何を求めているかではなく、自分自身が素直に美しいと思うことに自信をもつ。その感覚ってとても大事だと思いませんか? 芸術というと「センスがある・ない」の話題になりますが、センスは磨き方の問題で、特別なものではなく誰の中にも存在しています。こどもたちには「センス」を意識させるのではなく、自分にとってワクワクする、気持ちいい、ザワザワする、そう素直に感じるものを見つけてもらえれば。そのためにカメラは身近にある道具なので、こどもたちにはどんどんカメラを持ってほしいですね。


ワークショップでこどもたちが撮影した写真
――それはスマホカメラでもいいですか?
問題ないですが、スマホは触り慣れすぎていて、こどもはもはやカメラと認識していいないんですよね。本格的なカメラでファインダーを覗くと、自分が対象とちゃんと向き合っている感覚を得られます。「写真も撮れる道具」と「写真を撮る道具」とでは意識も全く違いますから、ワークショップではスマホカメラではなく、あえてカメラで体験してもらいます。何を表現すれば自分の伝えたいことが相手に伝わるか。そうした表現メディアとして考えた時に写真はとてもおもしろいので、こどもたちには写真本来の楽しさを味わってほしいと思っています。
――こどもたちの中からどんな表現が出てくるのか楽しみですね。
「表現」とはたまたまでき上がったものや撮れたものではなく、自分の意思と努力で創り上げるものです。正しい表現はどこかで葛藤があるものなので、その域にこどもたちをジャンプアップさせてあげたい、とも考えています。というのも、最近は「何でも自由にやらせるのが美術教育」みたいになってしまっていますが、それは違います。一つのテーマの中で、自分の感性をどう表現に落とし込み人に伝えるかを模索することは、経験として大切です。

本当の美術教育は柔軟な思考力を身につけるためのもので、それはこどもたちが将来何か新しいことを始める時に、色々な方向を検証してよりクリエイティブな方法を導き出すための訓練になるはずです。こどもたちが現代美術に本気で興味をもちはじめたら、その国の将来はとっても有望だと思うんです。
誰に対しても公平で、思い通りにはいかない写真の魅力
――そもそも、ご自身が表現手段として「写真」を選ばれたのはなぜですか?
根底には、父親の影響があるのかもしれません。僕の父がアマチュアの写真家だったので、当時の遊びといえばカメラをいじるかプラモデルをつくるかでした。こどもには好きなことをやらせたいという母親の方針で、うちには絶えずプラモデルがありました。一つでき上がったら次をつくっていいというルールで食事も忘れてプラモデルに熱中していたおかげで、学校の勉強は全然ダメでした(笑)。

ただ、カメラは父親にいじらされていた部分が大きく、実はこどもの頃は写真が好きではなかったんです。大学を中退して、グラフィックデザイナーとして活動する中で改めて写真の楽しさに気付いたので、本格的に写真の道に転向したのは30歳を過ぎてからです。好きなことで食べていけたら幸せだと思い始めたら、おもしろくて夢中になりました。そうこうしているうち50歳になり、じゃあ60歳まで、それでも続いていたら一生やろうと。
――蓮井さんにとって写真のおもしろさ、魅力はどんなところですか?
誰に対しても「公平」なところでしょうか。例えば、人生経験を積んだ80歳の人が撮った花の写真と、小学生のこどもが撮った花の写真を同じ大きさに引き伸ばして並べたとします。それを人が見た時に、「やっぱり80歳の人が撮った写真は違うね」となるかといえばそうでもない。絵画の場合、修練を積んだ人の表現力は素晴らしく見る人を圧倒しますが、どちらも作品として同じように並べた時に、フラットにいろんな人のいろんな言葉を引き出せるのが写真です。ある意味、重たくないんですよね。「80歳の人が撮った写真の方が意外に瑞々しいぞ」くらいの方がおもしろいと思いませんか?

――蓮井さんが写真を撮る理由は何でしょうか。
写真にはなかなか思い通りにいかないおもしろさがあるので、まだ辞めるのは早いというのが正直なところです。だから本当に自分の撮りたい写真が撮れた瞬間に巡り合うと、嬉しくて涙が出るんです。1枚の作品として切り取られた写真は、そこに写っている世界が暴風雨であろうと、どんなに悲惨な世界であろうと美しく見えたりします。それが写真の怖さであり、「写真てそれっぽっちのもの?」とも思うんですよね。僕が本当に見せたいのは切り取られた枠の「外側」で、暴風雨ならその暴風雨を感じさせたいのです。そういった意味でまだ勉強しなければならないこともあり、写真家として本当におもしろいのはこれからかもしれません。

――蓮井さんにとって写真とは。
写真を生業にしていますが、「写真は人生そのものです」というわけでもないんですね。シンプルに、「こんなにおもしろいものはほかにないぞ」という感覚です。なぜなら写真はものすごく大切ですが、写真に人生全てがあるのではなく、自分にとって人生の本当に大切な部分はもっと別のところにあるからだと思います。
例えば、モリウミアスとの繋がり。震災の支援から始まったことですが、モリウミアスでは復興のためだけではなく、あの場所をハブにしてもう一度環境を見直すことや、まちづくり、未来のための様々な取り組みを行っています。そんな姿勢にとても共感できるので、これからも自分の表現手段である写真を軸に繋がっていければ。そうした繋がりは、自分の信念をぶらさず生きていく上でも大事なものだし、なくてはならないものだと思っています。僕のワークショップに参加したこどもたちの中から、将来現代美術の作家が生まれた、なんてことになればまたおもしろいですよね(笑)。
蓮井幹生
1955年東京都出身。アートディレクター守谷猛氏に師事し、1978年日本デザインセンター入社。約3年間の勤務の後(株)スタジオ・マッセルを経て広告全般のアートディレクション及びレコードジャケットなどのグラフィックデザイナーとして活動。1984年から写真家に転向すべく独学にて写真を学び、写真家としてのキャリアをスタートする。1990年頃から広告写真家として様々なジャンルの広告作品に参加。2000年、ユニクロのキャンペーンで初めてコマーシャルフィルムを撮影。その後CFカメラマン及び演出家としても活動を開始。2004年ネスカフェエクセラ「夏の香り」にてACC特別賞ベスト撮影賞受賞。ADC、ACC、TCCなど参加作品に受賞歴多数。
撮影/渡邉まり子 文/開洋美